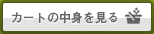【特集】新春!プリムラ・オーリキュラ特集
だんだんと日が長くなり始め、春の気配を感じる季節になりましたね。
新年の特集は、最近話題のプリムラ・オーリキュラの特集です。
プリムラ・オーリキュラは、産業革命の頃のイギリスで改良が盛んになった植物で、日本では見られないようなカラフルな色合いが注目の植物です。一見すると造花のようでもあり、実際に本場イギリスで飾られる時には、絵画を入れるような額縁の中にオーリキュラの鉢を飾って鑑賞することもあるのだそう。
ベルベットのような質感を持つ花びらや、白い粉を吹いた葉、均整のとれた花姿はずっと見ていて見飽きません。
みなさんも、宝石のようなお花を鉢に入れて飾ってみませんか?
今回の特集では、「プリムラ・オーリキュラってどんな花?」という疑問や育て方などにお答えします!
見れば見るほどはまってしまう、オーリキュラの魅力をご堪能ください!!
Q1 プリムラ・オーリキュラって?
元々のオーリキュラはアルプス、アベニン、カルパチカ山脈などの石灰岩地に生える原種のサクラソウです。アツバザクラ(学名Primula auricula:花色は黄色で中心部が白)と、生息地の重なるアルプス、ピレネーに生えるプリムラ・ヒルスタ(学名P.hirsuta :花色は淡いピンク〜ローズ)の自然交雑種がプリムラ・プベスケンスP.pubescensです。
この個体が変異に富んで面白いことから、16世紀頃の英国では人工的にブベスケンス交配が産業革命時の職工を中心とするフローリスト(育種家)によって盛んに行われました。本来、銘品オーリキュラは植物分類状、プベスケンスと変わりないのですが、園芸種として一定の約束事に沿って交配育種された品種をアルファベット大文字で書き始める「Auricula」とし、原種と差別したオーリキュラ群とする文化が生まれ、16世紀より昔から継承され、伝統的な園芸植物として現在まで根付いています。
Q2 プリムラ・オーリキュラの約束事ってどんなもの?
「Auricula」として認められる主な約束事には以下のようなものがあります。
1.花が円形に近く花弁がフラットで波を打たない。
2.花弁に切れ込みが少ないこと。
3.中心の基部が円形で歪みが少ないこと。
4.短花柱花であること。(雌しべが隠れて咲く種類)
その他、細かな約束ごとがあり、このような条件を満たさないものは、オウリキュラとして認められない。

Q3 プリムラ・オーリキュラの系統
400年にも及ぶ長い歴史の中で、プリムラ・オーリキュラの品種が多数作り上げられてきました。その系統は大きく分けて5つの系統に分かれています。その特徴をご紹介します。
(Shows Auricula)ショウ オウリキュラ
オウリキュラを代表する系統。花の中心が白粉で覆われ円環があり、花弁の色によりセルフ、エッジ、ファンシーなど大きく分け3タイプに分けられる。

(Show Selfs) ショウ セルフ
ボディーカラー(花弁の色)が単色で、中心円が白粉に覆われます。鮮やかな花色が多く、親しみやすい花が多いグループです。
花色別に、イエローショウセルフ、レッドショウセルフ、ブルーショウセルフ、ダークショウセルフ、アザー(その他)ショウセルフの5つのタイプに更に分けられます。

(Edged Auricula) エッジドオーリキュラ〜グレー・ホワイトエッジ
18世紀中ごろに出現して以来もっとも尊重された系統です。ボディーカラーは黒系でそれを緑色のエッジが取り囲みます。グレーエッジ、ホワイトエッジは、エッジに白粉がつきます。

(Edged Auricula) エッジドオーリキュラ〜グリーンエッジ
18世紀中ごろに出現して以来もっとも尊重された系統です。ボディーカラーは黒系でそれを緑色のエッジが取り囲みます。グリーンエッジは、白粉がつかないタイプです。

(Fancies Auricula) ファンシーオーリキュラ
ショウ系とエッジの中間型で1820年ごろに出現した品種。ボディーカラーは黄色か赤の明るい色で、その周りを、緑がかるエッジが縁取ります。
(Alpine Auricula) アルパイン系〜ライトセンタード
アルパインオーリキュラは、葉、花、中心円にも白粉がないのが特徴です。
花色は花弁の基部が濃く、先端に向け次第に淡くなるとても美しい花を咲かせます。
くっきりとしたあざやかな色合いが、ビギナーの方からマニアの方まで幅広く人気のある系統です。
アルパイン系には大きく分けて2タイプあり、ライトセンタードは中心円は白〜淡黄色で、花弁は青紫、ピンクになるタイプです。

(Alpine Auricula) アルパイン系〜ゴールドセンタード
アルパイン系には大きく分けて2タイプあり、ゴールドセンタードは中心円は濃黄色で花弁が赤、黄色、橙、茶などのタイプです。

(Stripes) ストライプ オウリキュラ
花弁中心部は白粉に覆われ、ボディカラーに絞りや縞が入るタイプです。その縞は緑で白粉が着くものが多いのですが、ストライプの入り方とカラフルなボディカラーとの組み合わせにより実に変化に富む花々を咲かせます。
例えば、単色のボディカラーに白緑色の粉をつけたストライプが入るもの、何色ものストライプが入り乱れるものなどがあります。
18世紀頃に人気を集めた系統です。

(Doubles) ダブル オウリキュラ
八重咲きタイプのオーリキュラです。2タイプの八重咲きがあり、スタンダードダブル…花色が多様で花弁が多く波打つように密集するタイプと、クラシカルダブル…花弁がやや少なく、シンプルな咲き方のタイプがあります。

(Border) ボーダーオーリキュラ
「Auricula(園芸品種上の約束ごと)」の条件を満たさない品種。比較的原種に近いタイプで、強健なものが多く育てやすい。花のバリエーションも幅広いので、個性的な品種が多いのが特徴です。ガーデンオーリキュラはこちらに含まれます。

Q4 プリムラ・オーリキュラの栽培方法
プリムラ・オーリキュラは、寒さにはとても強いのですが、夏の暑さが少し苦手な植物です。 暖地にお住まいの方は、夏越しに注意が必要ですが、暖地でも育てている方もたくさんいますので、工夫してがんばってみてください!
〜寒冷地の方へ〜
オーリキュラは寒さに強い植物ですので、気軽に育てることが出来ます。
ロックガーデンなどがあれば、露地植えも可能です。
ただ、品種によっては弱いものもありますので、そういった品種は鉢植えで育てた方がよいでしょう。
栽培のコツは、火山レキや鹿沼土などの水はけの良い用土を使用することと、 夏場はあまりたくさん水をやらず、表土が乾いたのを確認してから水をやるなど、乾かし気味に育てます。
年間を通して日向で育てます。(夏場は半日陰に取り込んでもよい)
〜暖地の方へ〜
夏越しのコツ
暖地の方は鉢植えにして栽培してください。
お買い求めいただいたら、植えてあるポットよりも一回り〜二回り程大きな素焼き鉢やテラコッタ鉢を使用して植えてください。使用する用土は、水はけが良い鹿沼土の中粒などが良いでしょう。
夏越しのコツは、夏場は直接雨の当たらない場所で雨よけすることと、なるべく風通しの良い半日陰などに置くとよいでしょう。
オーリキュラコレクション
パープル・セイジ
アザー・ショウ・セルフ
「パープルセイジ」は温かみのある赤紫色と白との色合いが美しいオーリキュラで、1966年にDerek Telfordが作出しました。
800円(税抜)
詳しくはこちらグレネルグ
ファンシーショウ
「グレネルグ」は暗赤と緑のコントラストの美しいファンシー・ショウで、1974年にDouglas氏の「ロルツ」実生株から出た品種です。栽培しやすい。
600円(税抜)
詳しくはこちらクルニエII
ファンシーショウ
「クルニエII」はさくらんぼ色と緑の可愛らしい配色のファンシー・ショウで、生育が旺盛で、栽培もやさしいほうです。
1985年にGordon Douglas氏が作出したもので、「ロルツ」×「ラジャー」の交配から出たものです。
600円(税抜)
詳しくはこちらアストラット
ファンシーショウ
「アストラット」は紅藤色〜明るい赤地に白緑色のエッジが入るファンシー・ショウのオーリキュラで、生育が旺盛で良く株立ちになるので、栽培し甲斐のある花。
600円(税抜)
詳しくはこちらドナ・クランシー
ファンシーショウ
「ロルツ」と「ラジャー」の交配でGordon Douglas氏により作出された花で、赤と緑のポップな色合いのファンシーショウです。増えやすく栽培しやすい花です。
600円(税抜)
詳しくはこちら