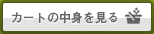【特集】ホトトギス特集
お盆が過ぎると、だんだんと寝苦しい夜も減り、涼やかな秋の到来を感じます。
夏の間屋外でのガーデニングを一休みしていた方も、秋が来るとソワソワ…お庭に出て、秋のガーデニングを楽しみたくなることでしょう。
今回は秋の到来を感じさせてくれるホトトギスの特集です。
ホトトギスや、ジョウロウホトトギスは、日本人好みの落ち着いた姿が魅力的な花が多く、台湾ホトトギス系の交配品種などは、花弁にホトトギス特有の斑点模様が少なくクセが無いので、
洋風のお庭やハンギングにも合いおすすめです。
今回は秋のシェードガーデンづくりや、鉢植え、寄せ植えなどに大活躍のホトトギスをたくさんご紹介します。
ホトトギスの特徴
ホトトギス(杜鵑草)はユリ科ホトトギス属の多年草で、日本をはじめ、東アジア(台湾・朝鮮半島)に19種が分布しています。
生育している場所は、山地の林内や、崖、傾斜地などの日陰に生えます。
日本に自生している種類は、13種あり、ホトトギス、キバナノホトトギス、タマガワホトトギス、
ヤマジノホトトギス、ヤマホトトギス、チャボホトトギス、タカクマホトトギス、ジョウロウホトトギス、キイジョウロウホトトギス、
スルガジョウロウホトトギス、サガミジョウロウホトトギス、キバナノツキヌキホトトギス、セトウチホトトギスがあります。
ジョウロウホトトギスや、ツキヌキホトトギスは、葉が下垂するタイプで、傾斜地に垂れ下がって咲く姿はとても風情があります。

ホトトギスの名前の由来
ホトトギスの名前の由来は、花弁に赤紫色の点を散りばめたような特徴的な模様が入り、
これが野鳥のホトトギス(杜鵑)の胸に入る模様と似ていることからつけられました。
葉に油を垂らした様な染みのような斑点が入るものがあり、その様子から「油点草」という別名もあります。

ホトトギス栽培
日本全国に分布し、耐寒性・耐暑性ともに強いので、とても栽培しやすく、親しみやすい山野草です。
寒冷地では、日当たりは春先は日が当たり、夏場は半日陰〜日陰になるような場所を好みますので、落葉樹の下などがおすすめです。
暖地では、風通しの良い日陰で管理してください。
台湾系のホトトギスは暖地ではとても強く栽培しやすいのですが、北海道では冬場の凍結で傷みやすいので、鉢植えの場合は
鉢ごと土の中に埋めてやったり、凍結から保護するなどの対策が必要となります。
植える場所は、水はけ良く植えるために、傾斜になっている場所や、石やレンガなどで囲って一段高く土を盛ったような場所に植えると
良く育ちます。
増殖はランナーや株で良く増えますので、春先の芽だし頃に株分けして増やします。
楽しみ方のいろいろ
育てやすいので、鉢植えや、寄せ植え、花壇、シェードガーデンなど色々な用途で活躍します。 下垂タイプは深鉢やハンギングにして、垂れ下がる茎の風情を楽しみます。洋風のガーデンなら、白花や、台湾系のタイプを選ぶと 洋風のガーデンにも合います。また、葉に斑が入るタイプや、カラス葉など葉色で楽しめるものは、カラーリーフとしての用途もあります。
〜日本各地のホトトギス〜
日本各地に分布するホトトギスは落ち着いた花姿が魅力的です。

〜茎が垂れ下がりエレガントな姿が魅力のホトトギス〜
茎が長く伸びて垂れ下がるタイプのホトトギスです。深い鉢に入れて長く伸びた花を楽しんだり、ハンギングや、ロックガーデンなどにも合います。

〜台湾ホトトギス系の交配種〜
台湾ホトトギスの血が入っているものは、花に模様が少なくすっきりしたものが多いのが特徴。 長く伸びた花茎は頭頂部で四方に分岐してたくさんの花を咲かせます。葉には艶があり細身です。

〜カラーリーフとして楽しめる品種〜
斑入り・カラスバなど、花がない時期でも葉の色で楽しめる、カラーリーフとしても魅力のあるホトトギスです。

〜小さいので鉢植えにもOKな品種〜
丈があまり大きくならず、鉢植えや、寄せ植えなどにも向くホトトギスです。